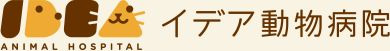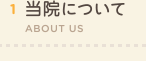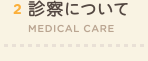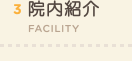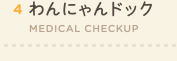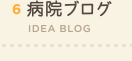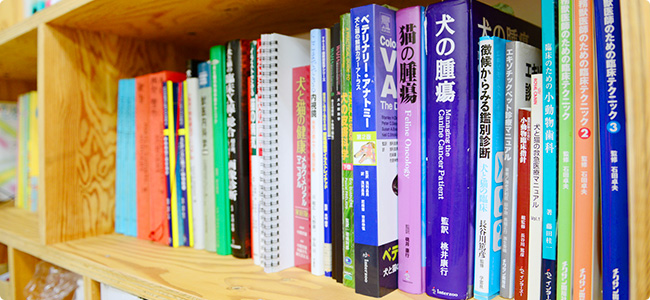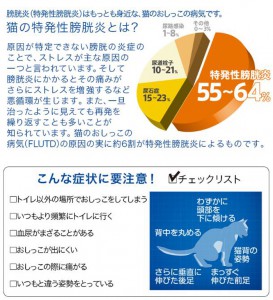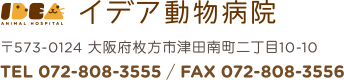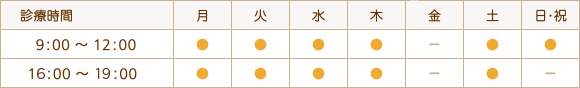診療のさなか、イヌに吠えるイヌ、イヌを怖がるイヌなど、
あたかも「自分のことを人間だと思っている」ようなイヌをよく見かけます。
これは、自然な現象なのでしょうか。
イヌは、最も古くから家畜化された動物と考えられています。
もともとは、イヌはオオカミやジャッカルと同じように群れで暮らす動物でした。
一万年以上も前から家畜化されてきたとは言え、
同族に対するコミュニケーション能力に長けた動物であることは変わりないはずです。
子犬には、「社会化期」という時期があるのをご存知でしょうか。
当院ではワクチンなどで来院された子犬さんには、必ずご説明させていただいております。
社会化期とは、生後3週~16週齢の、
様々な外界の刺激に免疫をつけやすくなる時期のことです。
混合ワクチン、狂犬病ワクチンなど「体のワクチン」と同様、
「心のワクチン」の接種時期ともいえるこの期間は、
健全な精神の発達にきわめて重要な期間といえます。
有名な「8週齢規制」は、
3~8週齢の社会化前期に親兄弟と引き離されることで起こる
精神の未発達を防ぐためのものです。
しかし、16週齢までの社会化期は、
8週・11週・14週の混合ワクチンの接種時期と重なっているため、
外に連れ出すことなく家の中だけで過ごしがちな時期でもあります。
すると、せっかくの社会化期に、外界に対する十分な免疫がつかなくなるため、
家族以外の、音、もの、動物などの外界の刺激に耐性がなく、
恐怖や不安を感じやすくなります。
それらは、イヌにとって、多大なストレス負荷となり、
吠える、唸る、噛み付くといった問題行動につながりやすくなります。
家族(人間)だけが自分の世界になってしまうのでは、
自分のことを人間だと思うのも無理はありません。
同じコミュニケーション動物であるヒトもしかり。
オオカミ少女に代表されるような現象が起こりうるのかもしれません。
以上、長々と書きましましたが、
つまりは、社会化がイヌの精神衛生上、
非常に大事なことだということです。
社会化期に、
抱っこしながら近所を歩いてみたり(外界に対する免疫)、
知人を家に招いたり(家族以外の人間に対する免疫)、
パピークラスを利用したりして(同族に対する免疫)、
いろいろなものに対する「心のワクチン」をあたえることはきわめて重要なことです。
そして、それは獣医師ではなく、愛犬の親である家族の皆様の手によって行われるものです。
(この時期は、伝染病に対する免疫は不十分なため、ドッグランなど
不特定多数のイヌが集まる場所に連れて行くなどして自由に遊ばせてはなりません。)
もちろん、この時期にしか社会化ができないわけではありません。
若い頃に比べれば時間はかかりますが、
社会化トレーニングは何歳からでも始めることができます。
社会化トレーニングは「心」のトレーニングです。
問題行動だけを見てどうにかしようとしてもうまくいきません。
愛犬の「心」に目を向けて、無理せずゆっくりと取り組んでいきましょう。
コンパニオンアニマルとして、
イヌの健全な精神の発展と人間社会への馴化が滞ることなく進み、
将来、人間社会に適応するための基盤を築くことは、ホームドクターの責務です。
今後も、パピークラスをはじめ、様々な教室を企画していこうと考えています。