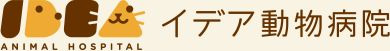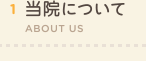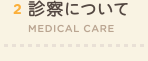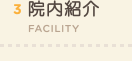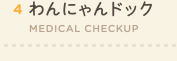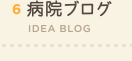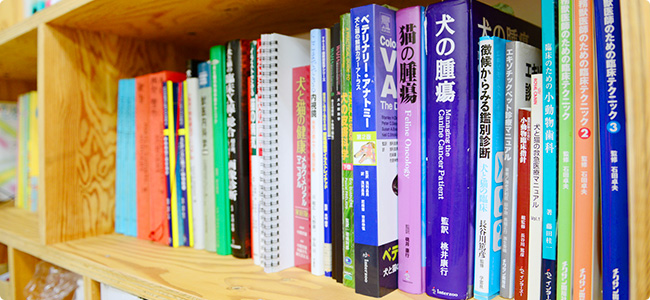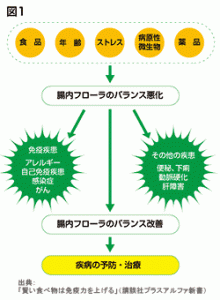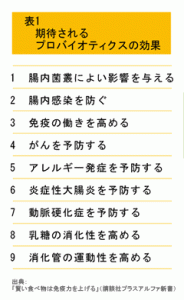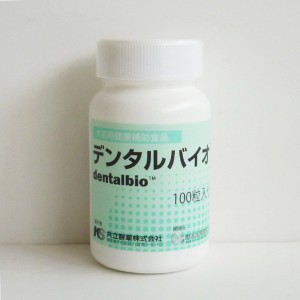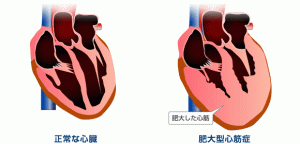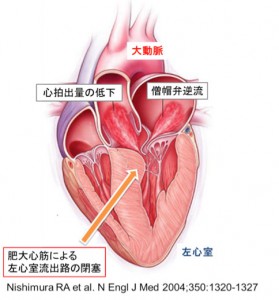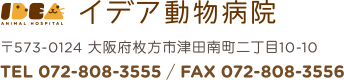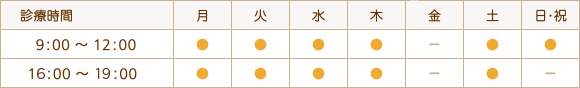昨今では、動物用の「サプリメント」が多数開発されています。
しかし、人間用は一般的になっているサプリメントですが、
動物にも与えているオーナー様は少ないようです。
今回は、サプリメントとは、いったい何かというところをお話します。
サプリメントとは、「栄養補助『食品』」のことです。
お薬のような治療効果を期待するのではなく、
体の栄養バランスを整え、
動物が本来持っている自然治癒力や免疫力を高めて、
病気にかかりにくい体を作る目的で投与されています。
あくまで「薬」ではなく、「食品」なのです。
消化器では、 プロバイオティクスが最近注目されています。
体の中には何十兆もの細菌が共存しており、
体調はこれらの細菌のバランスに左右されていると言っても過言ではないと言われています。
その中でも、体にとって良いはたらきをする善玉菌と悪いはたらきをする悪玉菌があり、
体内で陣取り合戦を繰り広げています。
プロバイオティクスは、善玉菌です。
善玉菌を摂取することで、
体の中の悪玉菌を減らし、体調を良い方向へ傾けてやるという目的で投与されます。
実際に当院では口腔内のプロバイオティクスを扱っておりますが、
口臭がなくなったと言われる方が多いようです。
他にも、目的別に挙げますと、
関節では、ミドリイガイ、コンドロイチン、グルコサミン、MSMなど
被毛においては、アミノ酸、ビタミン、ミネラル、不飽和脂肪酸など
肝臓では、ミルクシスル、ウコン、アミノ酸、ビタミンなど
不安症には、初乳タンパク、テアニン、メラトニンなど
免疫活性に、βグルカン、DMGなど
全般的なサプリメントとして、ビタミンやミネラル、消化酵素などが挙げられます。
与え方については、
チーズなどの動物の好むおやつと一緒に与えたり、
少量の水と一緒につるっと喉の奥に入れてあげたり、
フードと混ぜて与えたりすることが多いようです。
先ほどの口腔内のプロバイオティクスは、
胃酸や胆汁に弱いので、
粉にして歯肉に刷り込むのが1番良いようです。
最近では、動物が好む味付けがされてあったり、
カプセルなど形状に工夫がされてあったり、
特に嗜好性の高いチュアブルと呼ばれる
半生タイプのサプリメントも開発されています。
前述の通り、サプリメントはお薬とは違い、
投与してすぐに効果が出るわけではありません。
あくまで「栄養補助食品」として、長い間続けてもらうことが大事です。
病気になってからでは遅いので、
病気になりにくい体をつくり予防するという考えが重要なのですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最近、病院でスタッフルームに焼き肉などができるプレートを買いました。
そのため、毎週のようにたこ焼きや焼きそば、焼き肉パーティを企画 してくれます。
一般的に、動物病院のスタッフは、女性が中心です。
つまり、パーティは女子会となります。
女性の一般像として、もっとおしとやかなイメージがありましたが、
男性の集まりより会話がディープで、儚くもイメージは崩れ去りました。