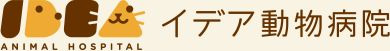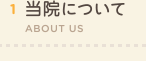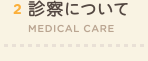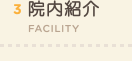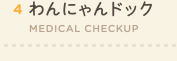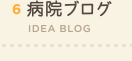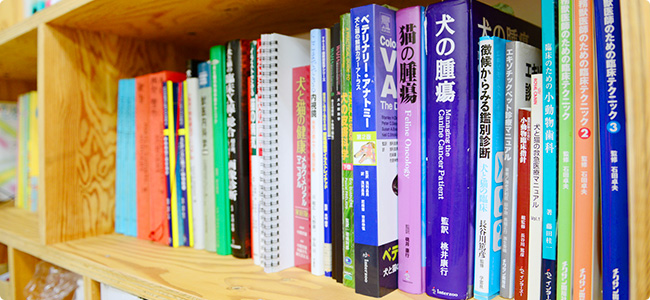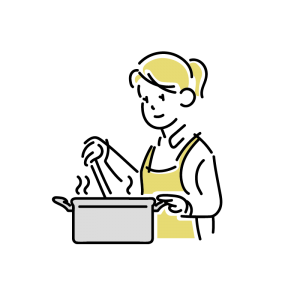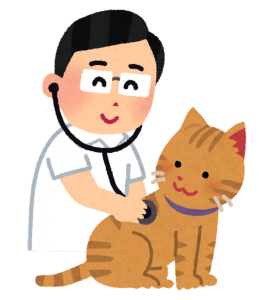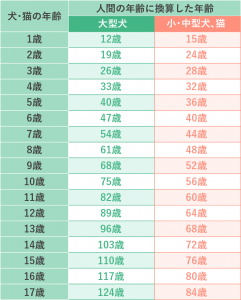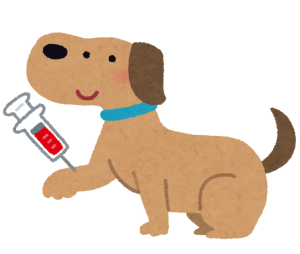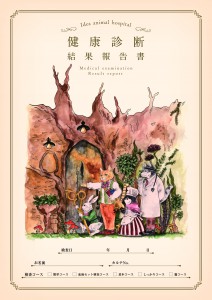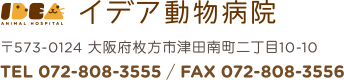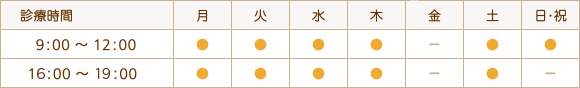みなさんこんにちは!
つい先日2022年度の仕事納めをしました獣医師の中垣です!
2022年もたくさんの方々、またワンちゃんネコちゃんたちと出逢えてとても幸せな年でした。
これからも、飼い主さまと動物に寄り添った医療を提供できるように日々精進して参ります!
さて突然ですが、
みなさんのお家のワンちゃんは「散歩」は好きですか?
おそらく、喜んで散歩に出かけてくれるよって子がほとんどだと思いますが
実際、「うちの子は怖がりで散歩が苦手なんです」と相談を受けることが少なくありません。
具体的には
いざ散歩に出かけても、
途中で歩かなくなってしまったり
他の人やワンちゃんを見ると必要以上に怖がったり、
その場から逃げようとしたりする、などなどです。
散歩に行く度に毎回ワンちゃんがこのような様子だと
飼い主さまの心理的にも
散歩に出かけることをためらってしまうでしょう。
ただ、ワンちゃんにとって「散歩をする」ということは
運動不足解消により肥満のリスクを回避したり
外の環境の刺激に触れることでストレス解消や脳が活性化されるなど様々なメリットがあります。
そのため、
怖がりなワンちゃんでも
散歩は楽しいものとだと思ってもらい
少しずつ慣れていってもらう必要があります。
しかし、散歩中に恐怖や不安から来る行動が見られたとき、
飼い主さまの対応の仕方次第では
逆にその不安や恐怖を助長させてしまう場合があります。
なので今回は、
ワンちゃんが不安や恐怖に関連した行動をした場合に
やってはいけない対応について、ご紹介させて頂きます。
(ここでいう恐怖に関連した行動は、攻撃したり、逃げたり、じっと固まってしまうことを言います)
怖がっている時にやってはいけない対応
①安心感を与える
安心感を与えるというのはつまり、声をかけたり、抱っこしたりすることです。
怖がっているワンちゃんに対して、そのような対応で安心感を与えてしまうと
その行動をとれば、安心することができるということを自覚し
さらに怖がるという行動がひどくなってしまいます。
具体的には、散歩中にワンちゃんが止まって動かなくなる場合などです。
ついつい抱っこをしてあげたくなるのですが
そうすると、余計に止まって固まるという行動が強化される、ということです。
そういうときは、
無理に引っ張らず、また声をかけることなく
黙ってワンちゃんが再び動き出すのを待ってみてください。
基本的に、恐怖に関連する行動が見られたときには
「ワンちゃんを見ない」「声をかけない」「触らない」ことが大切です。
②逃げる方向についていく
散歩中に他のワンちゃんと遭遇する場合が多々あると思いますが
怖がりなワンちゃんは自分でリードを引っ張って逃げて行こうとすると思います。
そうした場合も、一緒になってついて行ってしまってはいけません。
そうして結果的に、苦手なワンちゃんから遠ざかることができれば
その行動をすれば嫌な状況から逃れることができるんだと
結果的に怖がる行動がひどくなってしまいます。
できることなら、
苦手なワンちゃんが先に見えた時に
一度立ち止まって自分のワンちゃんの反応をよく見てください。
もし怖がっている行動が見られ、逃げようとするなら
ワンちゃんが逃げようとしている方向でも
相手のワンちゃんがいる方向でもない方向に歩き出して見てください。
ワンちゃんが決定権を持ち
逃げたい方向に行ったときに飼い主さんが後をついていくのではなく
あくまで飼い主さんが決定権を持って
歩く方向を決めながら相手の犬から遠ざかるようにすると
恐怖や不安をむやみに強くしてしまうことが少なくなります。
③叱ったり、無理にリードをひっぱる
こちらはシンプルですが
叱ったり、体罰を与えたり、リードを無理に引っ張ることをしてはいけません。
いずれもワンちゃんにとって苦痛や嫌悪感を与えてしまうため
恐怖がどんどん増幅し、散歩嫌いが加速していってしまいます。
今回は
「散歩が苦手なワンちゃんにやってはいけない対応」
についてご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
少しでも怖がりなワンちゃん、そしてその飼い主さまのお役に立てれば幸いです。
2023年度も、どうぞよろしくお願い致します!