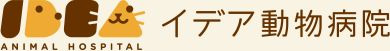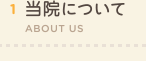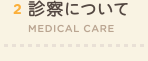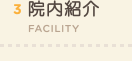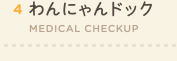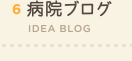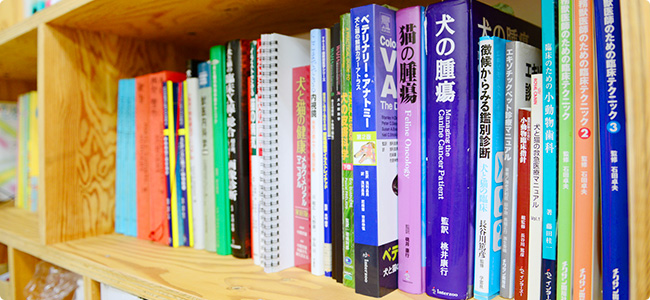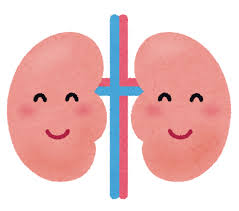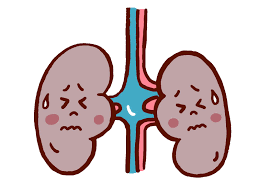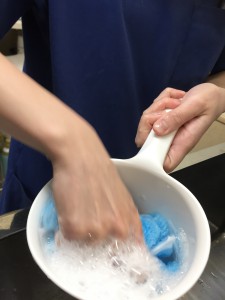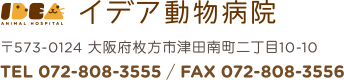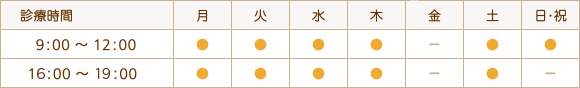こんにちは、獣医師の足立です。
最近めっきり寒くなって来ました。
夜、布団の中でぬくぬくするのが、
気持ち良い季節になって来ましたね♪
————————————————-
みなさん、
腎臓は何をしている臓器か知っていますか?
ご存知かもしれませんが、
尿を作っている臓器です。
それだけではなく
尿を作ることにより、体の老廃物毒素を排泄したり、
水分やミネラルなど、
体液のバランスを調節したり
血圧、カルシウム、造血を調節する
ホルモン等の産生もしています。
この腎臓の病気、高齢猫で多いのが、
慢性腎不全です。
10歳以上の猫で、30%はこの病気になっていると言われています。
動物病院でも、よく診る病気のひとつです。
この病気のやっかいなところは、
早期発見が難しい、というところです。
目に見える症状が出た時には、
かなり病気が進行していたり、
血液検査で、少しでも異常値になった時点ですでに
腎臓に残された機能が、30%以下になってしまっています。
腎臓が悪くなった部分は、もう元には戻りません。
なので、少しでも早く病気を発見することが重要です。
早くに治療開始をしてあげると、
腎臓が悪くなるスピードを遅くし、
元気で長生きすることにもつながります。
早期発見には、いくつか検査があります。
1 SDMA
血液で検査できるもので、一般的な血液検査項目より早期に異常値を示します。
2 尿検査
尿の濃さや、尿たんぱくの量により腎臓の機能を調べるものです。
8歳以上の猫であれば、
年1回でも、健康診断でこの検査を受けるか、
ワクチン接種時にでも、
検査を行うことをおすすめします。
もし何かご不明な点、気になる点があれば、
気軽に獣医師、もしくはスタッフにご相談ください。