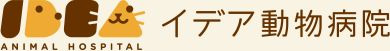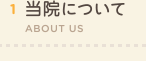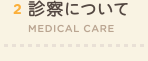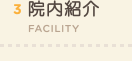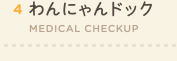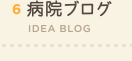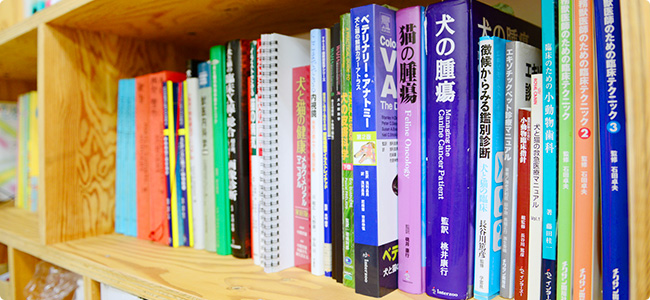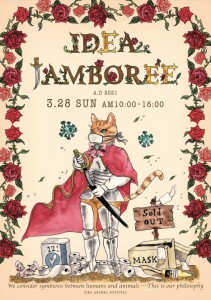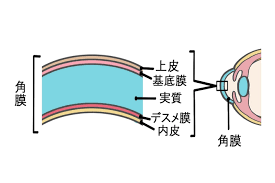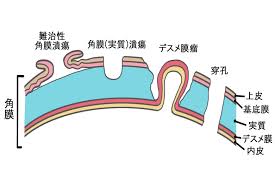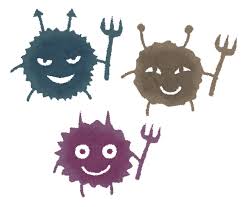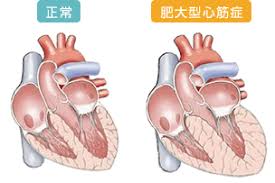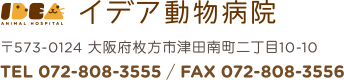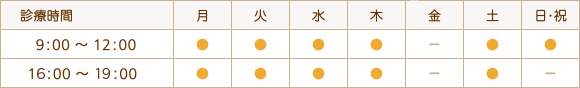こんにちは!獣医師の足立です。
早いもので、もう3月ですね。
先日、梅を見に大阪城公園に行ってきました。
もんのすごい種類の梅たちが満開で
全部きれいで、
すごく楽しいときを過ごすことが出来ました。
そんなゴージャスな梅もいいんですが、
近所を散歩途中に、
ふと家のお庭に植えてある満開の梅を見るのもいいですねぇ。
そこだけ春が一足先に来たみたいで、
あたたかい気持ちになります♪
———————————————————————-
さて、みなさん
3月28日は何の日か知っていますか?
そうです!
イデアジャンボリーの日です~!!
これはイデア動物病院主催のお祭りです。
いろいろなワークショップを行ったり、
ペットの写真撮影会や
グッズやパンなどを売る、いくつかのショップも出ています。
そこで、私も出し物をします。
キッザニア☆子供獣医師体験です。
内容、ひとつめは
わんちゃんの身体検査をしてみよう!です。
獣医さんは普段、わんちゃんのどんなところを見て
健康状態を把握しているんだろう?
ということを学んでもらいます。
内容、ふたつめは
超音波検査体験です。
普段、体の内臓を見る本物の超音波の機械を使って、
ゲーム感覚で体験をしてもらおうと思っています。
その他にも、
獣医さんって普段どんな仕事してるの?や、
どうしたら、獣医さんになれるか
獣医さんの仕事は他にもどんなものがあるかなど、
質問もしていただけます。
獣医師体験は、当日の予約制になっております。
当日、来場していただき
建物前に予約表があるので、
そこに名前を書いていただければ予約完了です。
→ 3/17より、数枠限定で事前予約の受付を開始しました。
予約したい方は、スタッフまでお問い合わせください。
コロナ感染拡大予防対策で、
10組(1組1家族子供2人まで)限定になっております。
ぜひ、みなさんお越しください~!
くわしくは、イデア動物病院のフェイスブックをご覧ください。