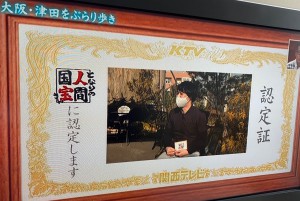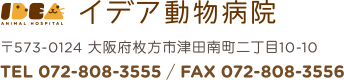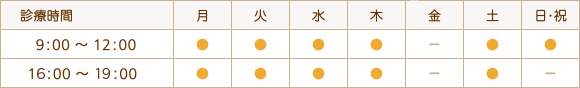6月も後半になり、夏目前ですね!(7月に入ってしまい申し訳ありません!!)
こんにちは、最近は家の前を流れる小川でホタルを見て帰宅するのが
日課になっている松本あかねです!
さて、冒頭でも夏目前とお伝えしましたが、この季節になると個人的に楽しみなのが
愛犬ディオ(通称;おじじ)の誕生日プレゼントとケーキを探すことです(^^)
顔つきもさながら、態度も大きくなったもんです(笑)
今年で14歳になるので健康にも配慮しつつ、喜んでもらえる物を探したいと思います!
ところで皆さん『犬 14歳』と聞くと何となくお年寄り、若くはないという
イメージはお持ちだと思いますが、人間の年齢の何歳に相当するかご存じですか?
ネットや書籍など諸説ありますし、大型犬・小型犬でも差はありますが
平均して犬の1歳で人間の12~15歳ぐらいと言われています。
2歳以降からは+4歳ずつくらいと言われており、
2歳で24歳、3歳で28歳・・・という感じで年齢を重ねていきます。
1歳までは子犬、2~6歳までは成犬、7歳以降は高齢・シニアと呼ばれます。
この年齢表に当てはめると、我が家のおじじは70歳超えなので立派なシニアですね(笑)
天気のいい日は自分から外に出たいと催促してきて
日向ぼっこをしながらお昼寝するのが大好きです!
生活環境や食事、ネットで何でも調べられるようになった今、
ペットたちの平均寿命はとても伸びています。
私が出会ったことのある最高齢は猫で23歳、犬で21歳です!!!
長生きの秘訣は小さな変化を見逃さない日頃からのコミュニケーションやスキンシップ、
そして、当院でも受けることが出来る健康診断がオススメです。
健康診断と聞くと人間の場合、中年になったら受けるものと思われがちですが
犬は人間よりも早く年を重ねていきます
来年でいっか、の来年は私たち人間のおおよそ4年後にあたります。
健康診断を定期的に受けるメリットは、その子個人の平均数値をモニターすることができ、
病気の早期発見・早期治療にも繋がります。
健康診断のコースによっては事前にご予約が必要なものもございますので
獣医師・スタッフまでお気軽にお尋ねください。
おじじも定期検診受けてますよ~!
『健診日の12時間の絶食だけがつらいよ~~泣』
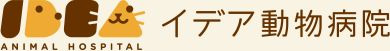
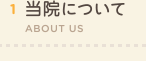
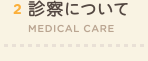
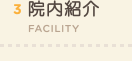
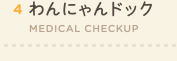



![LGRQ5358[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/LGRQ53581-224x300.jpg)
![IMG_4615[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/IMG_46151-300x225.jpg)
![IMG_4739[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/IMG_47391-300x274.png)
![IMG_3592[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/IMG_35921-300x225.jpg)
![IMG_3294[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/IMG_32941-300x225.jpg)




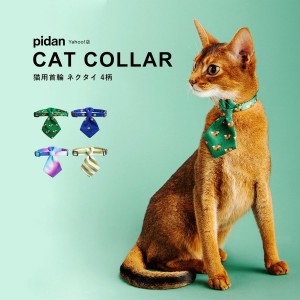


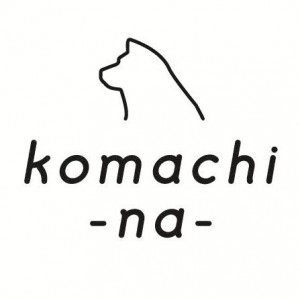



![IMG_5416[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/IMG_54161-300x225.jpg)




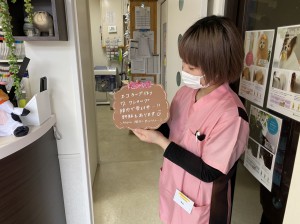























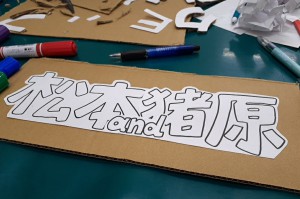
![DMPH3148[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/DMPH31481-300x199.jpg)

![IMG_0820[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/IMG_08201-300x168.jpg)
![IMG_0826[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/IMG_08261-300x168.jpg)