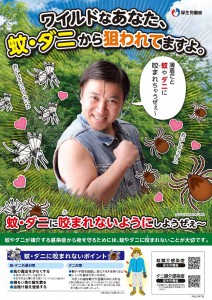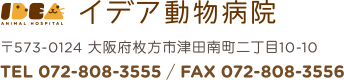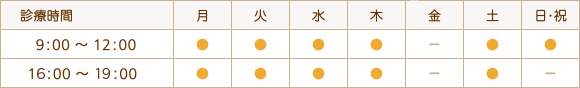こんばんは(*´∀`*)
トリマーのもとおちです\(○^ω^○)/
ブログの更新が遅くなって申し訳ありません!!
今回のお写真は、11月に来ていただいた
お客様たちです☆
イデアトリミングが初めてのワンちゃんもいて、
とても嬉しいです(*´ω`*)ノ゙
2回目のワンちゃんもたくさんでした!!
本当に本落うれしいかぎりです(^ω^人)
ムッくん☆
今日はバリカンですっきり!舌だしショット!
ポンくん☆
ハッピーバースディなポンくんは、
ポーズもバッチリです(*ゝω・*)
ゆずくん☆
初めましてのゆずくん、おりこうさんに
頑張りました (*・∀・*)
コタローくん☆
ふんわりもっふもふになりました☆
ひなたちゃん☆
シャンプーコースできてくれました♪
とってもおりこうさん(*ゝω・*)
ハルくん☆
スプレーでつやつやに!
二回目で慣れたものです☆
ウィリーくん☆
とってもいい笑顔をくれました(*´∀`*)
パティくん☆
「この角度が男前かな??」
まめちゃん☆
着こなしバッチリです♪
ゼットンくん☆
スプレー効果でさらつや (*σ´Д`*)
陸くん☆ 虎太郎くん☆
二人揃ってサンタさんとトナカイさん♪
モコくん☆
モヒカンがお似合いのイケワンコ!!
茅陽子ちゃん☆
舌をちょろーり♪抜糸も頑張りました(`・ω・´)
ももんちゃん☆
なんだか身構えたももんちゃんです(*¨*)
ミントちゃん☆
シャンプーコースでふわふわに♪
茶々丸くん☆
サンタコスチュームに慣れないのか
きょろきょろ。。
くりんちゃん☆
初めてでもとてもおりこうさんでした♪
ポーズもばっちり!!
るうくくん☆
おっとりのんびりのるうくくん、
くりんちゃんと仲良しです(*´∀`*)
11月後半から、地味にちょっとずつ
クリスマス仕様になっていったトリミング室。。。
今月からバッチリ完成した撮影セットでみなさんの
お写真を撮ることができます!!
コスチュームは、トリマーの直感で選んでおります。
もちろん、「こっちが似合う!!」と自信をもって
選んでおりますので、お楽しみに\(○^ω^○)/
2種類しかありませんが!!
たくさんのご予約ありがとうございました☆
12月の更新もお楽しみに(●´∀`)ノ
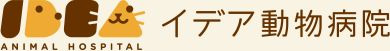
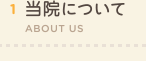
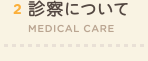
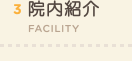
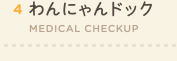



![IMG_1371[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_13711-e1511939985514-225x300.jpg)
![IMG_1387[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_13871-e1511940018441-225x300.jpg)
![IMG_1424[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_14241-e1511940050795-225x300.jpg)
![IMG_1430[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_14301-e1511940092578-225x300.jpg)
![IMG_1451[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_14511-e1511940135144-225x300.jpg)
![IMG_1470[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_14701-e1511940219985-225x300.jpg)
![IMG_1491[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_14911-e1511940296901-225x300.jpg)
![IMG_1512[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_15121-e1511940327129-225x300.jpg)
![IMG_1532[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_15321-e1511940366240-225x300.jpg)
![IMG_1536[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_15361-e1511940395992-225x300.jpg)
![IMG_1561[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_15611-e1511940430991-225x300.jpg)
![IMG_1595[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_15951-e1511940465605-225x300.jpg)
![IMG_1601[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_16011-e1511940502345-225x300.jpg)
![IMG_1608[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_16081-e1511942333566-225x300.jpg)
![IMG_1619[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_16191-e1511942360898-225x300.jpg)
![IMG_1643[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_16431-e1511942404936-225x300.jpg)
![IMG_1760[2]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/12/IMG_17602-e1512204486883-225x300.jpg)
![IMG_1763[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/12/IMG_17631-e1512204512740-225x300.jpg)




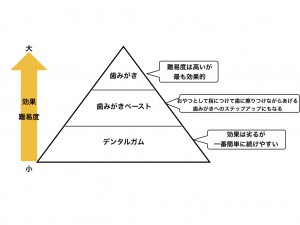








![IMG_0670[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_06701-e1509948732629-225x300.jpg)
![IMG_0697[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_06971-e1509948827307-225x300.jpg)
![IMG_0723[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_07231-e1509948870726-225x300.jpg)
![IMG_0769[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_07691-e1509948917223-225x300.jpg)
![IMG_0803[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_08031-e1509948969425-225x300.jpg)
![IMG_0879[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_08791-e1510205895983-225x300.jpg)
![IMG_0898[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_08981-e1510205938301-225x300.jpg)
![IMG_0913[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_09131-e1510205984903-225x300.jpg)
![IMG_0934[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_09341-e1510206025124-225x300.jpg)
![IMG_0971[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_09711-e1510206061985-225x300.jpg)
![IMG_0982[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_09821-e1510206119818-225x300.jpg)
![IMG_1073[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_10731-e1510640363749-225x300.jpg)
![IMG_1106[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_11061-e1510640411388-225x300.jpg)
![IMG_1155[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_11551-e1510640458481-225x300.jpg)
![IMG_1163[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_11631-e1510640493319-225x300.jpg)
![IMG_1231[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_12311-e1510640525711-225x300.jpg)
![IMG_1233[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_12331-e1510816795292-225x300.jpg)
![IMG_1249[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_12491-e1510816825268-225x300.jpg)
![IMG_1258[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_12581-e1510816862504-225x300.jpg)
![IMG_1270[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_12701-e1510816901984-225x300.jpg)
![IMG_1298[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_12981-e1510990377935-225x300.jpg)
![IMG_1323[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_13231-e1510990407987-225x300.jpg)
![IMG_1336[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/IMG_13361-e1510990439350-225x300.jpg)
![IMG_0179[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_01791-e1508212488627-225x300.jpg)
![IMG_0206[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_02061-e1508212529620-225x300.jpg)
![IMG_0217[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_02171-e1508571261462-225x300.jpg)
![IMG_0207[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_02071-e1508571228251-225x300.jpg)
![IMG_0248[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_02481-e1508571291834-225x300.jpg)
![IMG_0254[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_02541-e1508571326166-225x300.jpg)
![IMG_0274[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_02741-e1508571370213-225x300.jpg)
![IMG_0279[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_02791-e1508571402845-225x300.jpg)
![IMG_0287[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_02871-e1508571437385-225x300.jpg)
![IMG_0301[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_03011-e1508571469659-225x300.jpg)
![IMG_0319[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_03191-e1508571500939-225x300.jpg)
![IMG_0334[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_03341-e1508571550992-225x300.jpg)
![IMG_0346[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_03461-e1508571580595-225x300.jpg)
![IMG_0349[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_03491-e1508571627448-225x300.jpg)
![IMG_0395[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_03951-e1508824764670-225x300.jpg)
![IMG_0403[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_04031-e1508824794266-225x300.jpg)
![IMG_0414[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_04141-e1508824833984-225x300.jpg)
![IMG_0420[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_04201-e1508824869844-225x300.jpg)
![IMG_0425[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_04251-e1508824951571-225x300.jpg)
![IMG_0428[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_04281-e1508825007455-225x300.jpg)
![IMG_0456[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_04561-e1508825051193-225x300.jpg)
![IMG_0479[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_04791-e1508825101487-225x300.jpg)
![IMG_0532[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_05321-e1509347325563-225x300.jpg)
![IMG_0538[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_05381-e1509347374843-225x300.jpg)
![IMG_0544[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_05441-e1509347412235-225x300.jpg)
![IMG_0546[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_05461-e1509347446506-225x300.jpg)
![IMG_0596[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_05961-e1509347478866-225x300.jpg)
![IMG_0597[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_05971-e1509347507820-225x300.jpg)
![IMG_0609[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_06091-e1509435814921-225x300.jpg)
![IMG_0620[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_06201-e1509435849133-225x300.jpg)
![IMG_0641[1]](https://idea-ah.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/IMG_06411-e1509439513559-225x300.jpg)